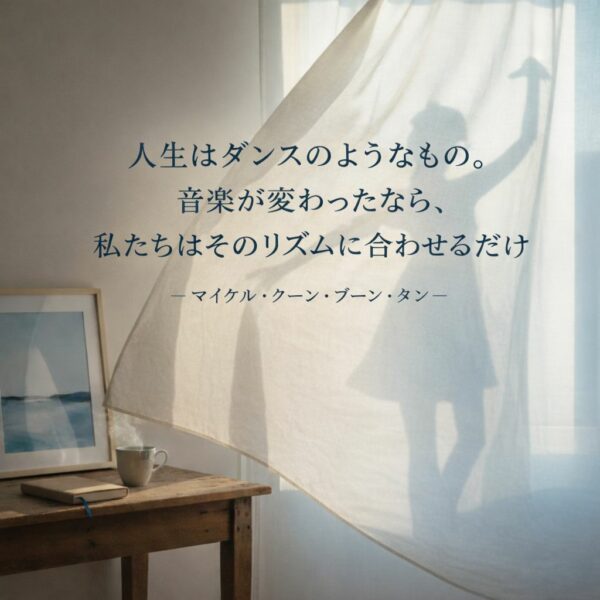額装の基本|作品を引き立てるフレーム選びと飾り方
― 作品と暮らしをつなぐ「額(フレーム)」というもうひとつのアート ―
アート作品を購入したあと、意外と悩むのが「どう額に入れて飾るか」。
「白い額がいいのか、木製がいいのか」
「作品との余白はどれくらい必要?」
「そもそも額は必要?」
額装(フレーミング)は、単に作品を保護するためだけでなく、
作品と空間、そして見る人のあいだをつなぐ”もうひとつのアート”です。
たとえば、同じ作品でもフレームを変えるだけで印象はがらりと変わります。
本記事では、Blue Coverで扱う実際の作品を例に、
「額装の基本」と「飾り方のヒント」を紹介します。
1. フレームは作品の“出会い”を設計するもの
フレームは「作品の枠」ではなく、「視線を導く装置」です。
欧米の美術館では、額そのものを“芸術作品”として展示することもあるほど。
たとえばルネサンス期の金の装飾額は、絵画の内と外をつなぐ「建築的な要素」として扱われていました。

聖母子像(ルネサンス期のフレーム)
出典:The Metropolitan Museum of Art
こうした歴史的な装飾額の系譜は、Brooklyn Museumの 「Art Frames Collection」でも詳しく紹介されています。→こちらからご覧ください。
一方で、現代のミニマルなフレームは、作品そのものの静けさや色を際立たせるための装置へと変化しています。

つまり額装とは、「どんな風に作品を見てもらいたいか」をデザインする行為なのです。
2. 素材・色・装飾の選び方:フレームが語る“時代と空間”
素材や色は、作品と空間の印象を決定づけます。
木製フレームは温かみを、金属フレームはクールで都会的な印象を与えます。
装飾の多い額はクラシックな雰囲気を作り出しますが、現代アートではシンプルな白やナチュラルウッドが主流です。
たとえば、そめやまゆみさんの銅版画《あおはたましいのいろ》では、作家自身が白い額を選びました。
青の濃淡が澄んで見えるように計算されたこの額装は、作品の呼吸を妨げず、むしろ空間に静かなリズムをもたらします。

《あおはたましいのいろ》
額装していない作品に、自分の世界を足すという楽しみ
Blue Coverでは、作家が額装を施した作品もあれば、あえて「額を付けずに届ける」作品もあります。
松田靜心さんの作品《フォレスト・レインB》(22×27.2cm)はその一例です。

鮮やかなピンクとグリーンの交わりが、春の雨上がりのような生命感を放つこの作品。
額を付けるとしたら──
– **ナチュラルウッド**なら、柔らかな季節の光を受けとめる穏やかな雰囲気に。
森の中の小窓のような印象。
– **白いフレーム**なら、色彩の躍動がより明るく浮かび上がります。
モダンな空間にもすんなり馴染みます。
– **黒いフレーム**なら、色が引き締まり、大人っぽいシックな印象に。
どんな額にするかを考えること自体が、作品との関係を深めるプロセスです。
額装済みを選ぶのも、自分でフレームを探すのも、どちらも正解。
それぞれの暮らしに合った“アートの迎え方”があります。
👉 あなたなら、どんなフレームを選びますか?
3. サイズと余白のバランスを考える
額装で意外と見落とされがちなのが、作品とフレームの“余白”です。
マット(白い内枠)を入れることで、作品が呼吸するように見えることがあります。
また、壁との距離感も重要です。
大きすぎる額は圧迫感を与え、小さすぎると埋もれてしまいます。
リビングのような空間では、壁に余白を残すことで全体のバランスが整います。
この“余白をデザインする”という感覚こそ、額装の面白さです。

4. 飾る場所と光のバランス
どんな額を選んでも、光の当たり方で印象は変わります。
自然光の下では柔らかく、スポットライトではドラマチックに。
**注意したいポイント**:
– **直射日光が当たる場所は避ける**:紙作品や版画は色褪せの原因になります。
– **金属フレームは反射に注意**:窓の正面に掛けると、
光が反射して作品が見にくくなることもあります。
– **湿気の多い場所(洗面所、浴室近く)は避ける**:カビや変色のリスクがあります。
額を掛ける高さは、目線より少し上が理想。
視線の延長線上に作品があると、部屋全体が“整って見える”不思議な効果があります。

5. 額装もまた、作品を守る投資
最後に、額装は“見せ方”だけでなく、“守ること”でもあります。
紫外線・湿気・埃など、作品を劣化させる要素から保護してくれる。
特に紙作品や版画では、額装がその寿命を決めることもあります。
Blue Coverでも、作家が「作品に最も合う額」を選ぶことがあります。
それは、美しく見せるためであると同時に、作品を未来に残すための選択でもあるのです。
🕊 まとめ
フレームは、作品と暮らしの“架け橋”です。
どんな額を選ぶかで、作品はまるで違う表情を見せます。
アートを飾るという行為は、ただ眺めることではなく、「作品との関係を育てること」。
あなたの部屋に合う額を探す時間こそ、アートを自分のものにしていく第一歩です。
—
**最後に、ぶっちゃけた話を。**
ここまで額装の「基本」や「セオリー」をお伝えしてきましたが、
最も大切なのは、**あなた自身が心地よいかどうか**です。
「額は不要」と感じるなら、それも一つの答え。
「これだ」と納得した額(不要も含めて)なら、どんな選択も正解です。
ルールに縛られすぎず、自由に楽しんでください。
👉 そめやまゆみ《あおはたましいのいろ》を見る
👉 松田靜心《フォレスト・レインB》を見る
**🌍 English Version | The Art of Framing: How to Choose and Display**
**Framing is more than protection—it’s part of the artwork itself.**
At Blue Cover, we believe that frames are not just borders,
but “devices that guide the viewer’s eye.” From ornate Renaissance gold frames to minimalist modern designs, framing has always been about shaping how we encounter art.
**Key Points:**
- **Material & Color Matter**: Wood frames bring warmth; metal frames create a modern, urban feel. White frames highlight colors, while natural wood adds softness.
- **The Joy of Choosing Your Own Frame**: Some works, like *Shizumune Matsuda’s “Forest Rain B,”* arrive unframed, inviting you to complete the vision. Would you choose white for brightness, wood for warmth, or black for sophistication?
- **Light & Placement**: Avoid direct sunlight to prevent fading. Hang art slightly above eye level for the best visual balance.
- **Protection as Investment**: Framing shields artworks from UV rays, moisture, and dust—especially crucial for prints and works on paper.
Choosing a frame is not an afterthought, but a dialogue between art, space, and the viewer.
→ [View Mayumi Someya’s “Blue Soul’s Color“]
→ [View Shizumune Matsuda’s “Forest Rain B“]