第7章 愉快に生きるための思想 -仏教 タオイズム アナキズム-

序:なぜ私は仏教に惹かれたのか
なぜか、小さいころから仏教が好きだった。とても不思議なんだ。何しろ両親は宗教とは縁のない普通のサラリーマンと専業主婦だったからね。今でも鮮やかに覚えているのは、
中学の運動会で応援のための大きな幟の旗を作ることになり、なぜか私が一人で(たぶん)「南無阿弥陀仏」と大きな字を筆で描いた。先生も周りも何も反対しなかったのだが、どうしてそんな題目を書いたのか? いまだによく分からない。別に親鸞や浄土真宗の信奉者ではないし(今でも)。摩訶不思議な行動だ。何だか得意になってその旗を振り回して高揚した気分に包まれた感触をよく覚えている。
仏教の核心 ― 苦からの解放
そして、大学生の時には財布に四諦八正道の文を書いた紙を後生大事にいれていた。これまた、どうしてか? いまだによく分からない。恐らく、人生が苦であること、その苦を克服する希望が多少なりともあることを無意識のうちに感じて、お守りのように抱えて安心しようとしたのかもしれない。
そもそも仏教の教えは単純に言えば、四諦八正道って呼ばれる。
- 人生は苦である。
- その原因は自分への執着にある。
- 執着を離れて苦から解放される道がある。
- そのための八つの正しい道がある。中でも、最も大切な道が正しい瞑想である。
この四つが四諦だね。つまり、仏教の教えと座禅やマインドフルネス瞑想の実践は、本質的には自己へのとらわれから離れるためにあるんだよね。自己へのとらわれ=執着が苦しみを産み、静かに愉快に生きることを不可能にしてしまう。私がどこかで仏教に惹かれたのは、何だか分からない苦しさや生きづらさを感じており、そこからの解放への道のりがシンプルに分かりやすく示されていたからだと、今では思う。
それから、よく言われる仏教のエッセンスは、「諸行無常」と「諸法無我」。これも自己へのとらわれから少しでも解放され、愉快に生きるためのシンプルな考え方=哲学だね。私は何か嫌なことがあると、おまじないのように、この二つのテーゼを心の中でブツブツとつぶやいている(変な人だよね)。
「諸行無常」は、前述したごとく私の生きる上でのテーマ「流れる身体・流れる心」と即繋がっている。あらゆることは流れ流れて変化し続ける。流れに逆らったり、流れを止めようとするから無理が生じる。あるがままに、流れるままに。小さな流れの川が大海に辿り着くように。流れに乗ってリズムよく踊り歌い続けることが愉快に生きるコツだろう。
「諸法無我」は少し難しい。実体としての独立した自分は存在しない。関係性としてのみ、自分は存在する。例えば、私は空間的には、酸素や大地や植物や地球や宇宙があるからこそ存在している。また、時間的には両親、そのまた両親、そのまた両親~と何代かさかのぼっただけでもすぐに何万人かの祖先がいる。その内の一人でもいなければ、自分は存在しないわけだ。こう考えると、空間と時間の関係性の網の結び目で奇跡的に存在しているのが我々と言えるだろう。だからこそ、自己にとらわれて、あたふたともがくのは実にもったいない。
だが、哀しいかな? われわれの意識の在り方としては、このような曖昧な関係性としての自己を意識しづらく、あたかも確固とした自分がいて、自分を中心にして世界が回るかのように感じるようになっている。いわば、本来の自分をごまかすように脳が働いて、他者との比較や世間を気にして右往左往するような幻の自分にこだわるよう条件づけられていく。
理屈でこの考えを受け入れても、なかなかに脳は手強いので、実感として関係としての自己を感じるのは実に難しい。だからこそ座禅やマインドフル瞑想が必要になるというわけだ。
「色即是空」も、あらゆる現象や物は実体がない、空である。関係性としてのみ存在している、としみじみ味わうための呪文なのだろうね。また、難しいとされる縁起の考え方も、いろいろな縁=条件が重なり合って、自分という身体も自分という意識も立ち上がっていく、さまざまな条件の重なりがなければ自分は存在しない、と考えればよろしい。
愉快に生きるための仏教としては、難しいお経や悟りへの考察は必要なく、上記の考え方さえ理解し、あとは楽しみながら瞑想すれば、それで十分だ。苦しい座禅や難しいお経や厳しい作法やルールは必要ない、というのが「なんちゃってブッディスト」の私のスタイルだ。
マインドフルネスとの違い
ところで、今流行りのマインドフルネス瞑想は、とらわれからの解放ではなく、何かを得るため、つまり健康や成果や幸せをGETするためになっている。本来の仏教は、GETではなく、GIVEだよね。エゴを滅して、他者へ慈悲を施すわけだからね。
そんな仏教の思想を抜いた、流行としてのマインドフルネス批判が仏教界から出てきたのは当然といえば当然だ。自我を肥大化してしまう恐れすらあるのだからね。なので、マインドフルネス瞑想の良心的な指導者は、その辺を踏まえながら<慈悲の瞑想>を取り入れたりしてバランスを取りつつある。
では、簡単な<慈悲の瞑想>を紹介する。
- 困っていたり、苦しんでいたりする対象を決める。身近な個人でもいいし、もっと広い対象でもいいよ。例えば、飢えて苦しんでいるすべての子供たち、原発で未だに自宅へ帰れない人たちなど、自分が少しでも慈悲を与えて助けたいと思う人たちを選んでみて。
- その対象を明確にイメージし、彼らの苦しみをしばらく感じてみよう。
- 鼻から息を大きく吸いながら、彼らの苦しみが自分の中に入るようイメージする。
- その苦しみをお腹に集めて慈悲の光で包み込み、苦しみが溶け去るようイメージする。
- その対象に向かって口からゆっくり深く息を吐きながら、慈悲の光が彼らを包み込み、苦しみが溶け去るようイメージする。
この呼吸法を10分から20分繰り返す。すると不思議なことに、相手が慈悲の光に包まれて少しずつ癒されていくのが何となく実感できる。そして、自分のエゴも少しずつほどけていくのが分かるようになる。日常生活に忙しくていつもこんな瞑想はできないかもしれないけど、余裕のある時には、普通のマインドフルネス瞑想の後にでも是非とも試してみて。自分の幸せ、静けさだけでなく、困って苦しんでいる人たちの幸せを願うことが凄く重要だって良く分かるよ。

愉快に生きるためのタオイズム(タオイズムの智慧 ― 水のように生きる)
タオイズムとは老荘思想のことだ。天と地が生まれる前の根源的な何か? 宇宙全体を創造したエネルギーみたいなものを、仮にタオ=道となずけた。英文学者であり詩人の加島祥造さんが、難しいとされた老子の道徳経を自由現代語訳にして、随分読みやすく理解しやすくなり大きなインパクトを受けた。私が40歳から心酔して学んだロジャーズやジェンドリンの人間性心理学やカウンセリング理論は、実はタオイズムをベースにしている。「あるがままを生きる」「過去や未来にとらわれず今ここを生きる」が共通点だ。カウンセリングの、とても自由で柔軟で愉快な考え方の基本が老子にあったのだから、びっくり仰天だね。
個人的には、仏教への興味から老子のタオイズムに至り、さらにカウンセリングやマインドフルネスに辿り着いたのだから、何だか不思議な川の流れに乗ってここまで辿り着いたような気がして、愉快きわまりない。禅は中国で、インド伝来の仏教と中国オリジナルの老荘思想が融合して出来上がった、という説もあるから、この流れは自然なものだったのだろうね。
タオイズムの基本のコンセプトは「あるがままに生きる」「争わない」「前に出ない」「無為自然(余計な計らいをしない)」「頑張らない」「求めない」「流れに身を任す」「今ここを生きる」などだ。こう並べただけでも、何だか愉快でうっとりとなってしまうのは、私だけかな?
最初に加島さんの詩を読んで妙に納得したのは、名前のマジックだった。
「美しいと汚いは、別々にあるんじゃない。
美しいものは、汚いものがあるから、美しいと呼ばれるんだ。
善悪だってそうさ。善は悪があるから、善と呼ばれるんだ。
悪があるおかげで、善があるってわけさ。
同じように、ものが「在る」のも、
「無い」があるからこそ、ありうるんでね。
お互いに片一方だけじゃあ、ありえないんだ」
鶴見俊輔が「悪の自覚」の必要を繰り返し述べていたけど、正義や善をどんどん突き詰めると、オセロのように悪が忍び寄り反転してしまう。オウム真理教の事件が、善が悪に反転してしまった良い例だろう。このタオマジックを実感として味わえれば、人と競争して争ったり、お金や権力を求めたり、頑張って人より前に出ようとしたり、思い通りに相手を支配しようとしたり、なんて欲望はスッーと萎んでいくはずだ。これまで述べてきた、「愉快に生きるには不愉快が必要」という逆説テーゼの源流がタオイズムなのだね。
「天と地のむこうの道(タオ)につながるもうひとつの自分がある。その自分に戻れば、人にあざけられたって褒められたって「ふふん」という顔ができる。たかの知れた自分だけれど社会だって、たかの知れた社会なんだ。タオの働きをよく知る人は、何か行為をする時、争わないのだよ。争わないで、するのだよ」
「理屈はそうだろうけど、そんなに上手くはいかないよ」という声ももちろんあるけれど、そこはそれ、やはり究極には世界を成立させている根源のエネルギー=タオを少しでも感じられるか? がポイントになる。そのための手段、メソッドが気功や太極拳なのだろう。仏教の教えを身に着けるために座禅が必要だったように、タオイズムの教えを身に着けるには気功や太極拳が必要なのだろうね。

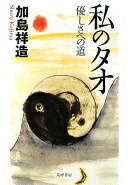
また、タオイズムでは、水がメタファとしてよく登場する。「上善如水」「明鏡止水」という美味しい日本酒があるが、これもタオ由来の言葉なんだ。知ってた? 二つとも私の好きな端麗辛口の水のような瑞々しい味わいのあるお酒だ(余談)。水のように千変万化、柔らかく下流へ流れていくことが人生の土台となる。清らかな水のようにゆったりまったり「下へ、下へ」と余計な計らいをせずに流れていくこと。もちろん、善悪や陰陽を区別したり、私心や欲求に囚われることは水ではなく岩のような固さや脆さとなる。何にも囚われず無為であることで、水のような流動性と母なるタオの源へと立ち返ることが肝心なのだね。柔よく剛を制するが原点だね。
「無為とは、なにもしないことじゃない
誰も、みんな、産んだり、養ったり、作ったりするさ、
しかし、タオにつながる人はそれを自分のものだと主張しない。
熱心に働いてもその結果を自分のしたことと自慢しない。
頭に立って人々をリードしても、けっして人を支配しようとはしない。
頭であれこれ作為しないこと、タオに生かされているのだと知ること、
それが無為ということだよ。
なぜって、こういうタオの働きに任せたときこそ、
ライフ・エナジーがいちばん良く流れるんだ。
これがタオという道の不思議な神秘のパワーなんだ」 (老子道徳経第十章)
こう見てくると、タオイズムには愉快に生きるための智慧がここぞとばかり、滔々と流れ溢れかえっている。「ありがたや、ありがたや」だね。

愉快に生きるためのアナキズム(アナキズム ― 権力への抵抗として)
大学時代、「必ず学ぶべき、自分なりの考えを持つべき二大テーマがある」と先輩や友人からしつこく言われた。一つは宗教とどう関わり、消化していくか? もう一つはマルクス主義とどう関わり、消化していくか? こんなテーマは今や死語となってしまったのかもしれないが、当時の大学生にとっては最大の関心事というか、生きていくうえでの最重要課題だったのだね。
宗教については、ここまで述べてきたように、生活の哲学としての仏教(宗派は基本的に興味ない)とタオイズムが私なりの一応の答えだが、随分と時間がかかってしまった。まあ、愚かな私としては、こんなもんだろうと納得がいく。
もう一つの大きなテーマ、マルクスさん。こちらは、個人的には意外と早くからケリをつけていた感がある。私が個人的に影響されたのはマルキシズムではなく、アナキズムだった。「あらゆる組織は腐敗する。どんな革命的な組織でも」。これはアナキズムの基本的な考えだ。また、アナキズムの一般的なイメージとしては、無政府主義なのだから、すべてをぶち壊し、秩序をビンビンと紊乱するラジカルな暴力集団、最左翼、テロリズム、「大コワッ」といったところだろうか?
しかし、今若者の間ではアナキズムが再評価されている。その際アナキズムの定義として「無政府主義ではなく、無支配主義。ゆえに権力と戦うのではなく、あくまでも権力に抵抗する」というテーゼが若者の心をつかんだのだ。何よりも自由で愉快な生活に根差した考え方と運動への再評価だよね。大杉栄や伊藤野枝をアイドルのごとく推し活にしている若者もいるぐらいだから、時代は変わった、実におもろいね。
私が個人的にアナキズムに惹かれたのは、二点からだった。
一つは、高校時代の唯一信頼できる先生が「アナキズムだけには嵌るな」と口を酸っぱくして言っていた。私が通った埼玉県の熊谷高校の近くには石川三四郎という素敵なアナキストがかつて存在したし、反権力の自由を守る運動だった秩父事件にも興味を持っていた私は、天邪鬼から「それならアナキズムを学んでみよう」と思いたったのだ。
もう一つは、大学時代にジョージ・オーウェルの「カタロニア讃歌」を読んで感動した経緯がある。あまりにもあまりにも人間的で感性豊かで勇気と心意気に溢れていたアナキストに対して、スペイン共産党は敵=ファシズムと戦う前に、まずは身内のアナキストを攻撃したのだ。もちろん、その結果スペイン市民革命は敗北し、ファシズムが世界中に拡がる悲惨な結果になったのは言うまでもない。
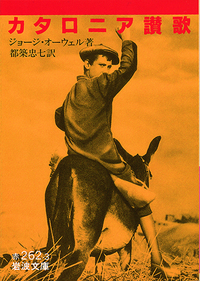
また、唯一私が多少なりともコミットしたべ平連(ベトナムに平和を・反戦連合)は、鶴見俊輔と小田実という思想的にはアナキストが発起人であった。出入り自由、誰が名乗ってもいい、全員参加の直接民主主義的な討議ですべてを決めていく。縦の権力構造は極力排除しようという強い意思が働いていたのだ。当時の運動で最もラジカルだったアメリカの脱走兵援助という権力への抵抗運動がそれなりに機能したのも、アナキズムが思想的背景にあったからだと思う。私は1970年の安保前後のたった数か月だったが、熊谷ベ平連を友人と立ち上げて、何度かデモに行ったことが思い出される。
ちなみに、鶴見俊輔を好きなのは「悪党の自覚」を彼が口酸っぱく述べていたからだ。
自らが善でその善を完遂するために、自分とは異なる善は悪だとして攻撃する。正義をどこまでも追及すると、いつの間にか悪が忍び寄るというパラドクスだね。自分は間違うし、他者を支配したいという悪の部分、権力欲が否応なくあることを認めない思想や組織は否応なく腐敗するだろう、と彼は言う。何しろ彼は正義の味方=母親(有名な政治家、江藤新平の娘)からの愛ゆえの正義の呪縛を逃れるために、殺人以外のありとあらゆる悪に手を染めたというのだから、えらいね。しかも小学生の時からだ、「負けたな」と思った。私の悪はせいぜいカンニングするぐらいだったからね。
国家に絡めとられない自由、システムへの抵抗としてのアナキズムは個人の内面だけでなく、社会とどう愉快に関わり生きるか? のためのベースにもなるはずだ。
希望があるとすれば、国家に収斂されない、むしろ国家を利用し、国家を超越するようなささやかな渦をそこら中に巻き起こすことか? 台湾のデジタル担当大臣、オードリー・タンは自らを保守的アナキストと名乗っている。すでにある暮らしの中にアナキズムのエッセンスを取り入れる。既存の国家の体制をうまく利用する。国家の中にアナキズムの空間を少しずつ広げていく。様々に異なる価値観が混然としていて、「一つの正しさ」を押し付けられることのない、強制から解放されたアナキズムを実現するには、誰もが安全だと感じる自由でオープンで平等な居場所が必要だ、とタンは述べる。
確かに、家庭や学校に、また社会全体に、安全で自由で楽しい居場所がないから、若者も老人も子供も病んでいく。抑圧や束縛や理不尽な権力に抵抗できるには、そのような居場所とお互いに上手に依存し合える横の関係が絶対に必要だろう。カウンセリングの場でも信頼し合える安全基地を作るのが最重要課題だが、それを地域に、社会全体に繋げていくことが今後の課題なのだろう。そのような暮らしのアナキズム的な動きが至る所で芽生えつつあることが、唯一の希望と言えるかもしれない。
筆者 大澤 昇 プロフィール
日本産業カウンセラー協会認定シニア産業カウンセラー・臨床心理士。
1971年 早稲田大学卒業、2004年 目白大学大学院修了後、企業内カウンセラーや学生相談室カウンセラー、また大学講師として様々な経歴を持つ。
現場で培った経験を活かし、メンタルヘルス講師や、教育カウンセリング講師、大学の非常勤講師として活躍中。
また数多くの論文・著書を発表しており『やすらぎのスペース・セラピー 心と体の痛みがあなたを成長させる』『心理臨床実習』『トラウマを成長につなげる技術』等の著書がある。




